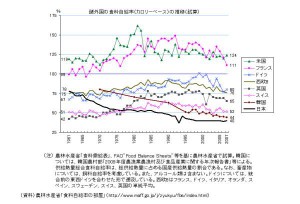各国の食糧自給率を知った上で議論しよう

TPPをめぐり、ようやく最近になって、、
「農業だけの問題ではない」という情報が出回るようになった。
ちなみにTPPとは何かについては、
私の.10月18日の日記、
「TPP議論を主体的な日本づくりの機会に!」
に、端的にまとめているので、
そちらをぜひ、ごらんいただきたい。
そのうえで、もう一度、農業問題。
すでに多くの方がご存じのように、
わが国の食糧自給率は、カロリーベースで39%である。
この数字が先進国中、最下位であることを、まず知ってほしい。
では、他国はどうか?
以下に主要先進国の食糧自給率推移のグラフを掲載する。
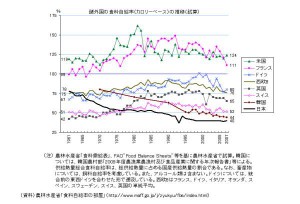
ざっと抜き書きすれば、
上から、
●アメリカ 124%
●フランス 111%
●ドイツ 80%
●西欧8カ国 76%
●イギリス 65%
以下略
となっている。
自給率が100%を越えると輸出超過となり、
反対に100%をきると輸入超過ということになる。
つまりアメリカやフランスは、自国内での食糧が余剰状態であり、
あまった作物を他国へ売っているということである。
ちなみにアメリカは世界最大の食糧輸出国だが、輸入も多いので、
相殺すると24%程度の超過におさまることになる。
一方の日本は、食糧の6割強を他国から買っていることになるが、
輸出している品目もあるので、実質的な輸入依存度は、その数値以上に高い。
ここからが要点だ。
自国の食糧が不足していれば、輸出するにしても、
おいそれと低価格で提供するわけにはいかないが、
すでに自国民の分は確保できていて、余っているのであれば、
ほんのわずかの利益で他国へ売っても、損な話にはならない。
ということである。
みなさんも実感があると思うが、
アメリカ産の農産物などは、非常に安い。
日本に入ってきた段階で関税をかけて高くしているのに、
それでもまだあの安さである。
時折、日本の農作物が相対的に高値なのは、
日本の農家の努力不足のように誤解する人がいるが、そうではない。
日本とは比較にならないほど広大な耕作地を持つ各国が、
そのスケールメリットを発揮して低コスト→低価格の作物を世に出し、
なおかつ、
「余っているんだから、さらに安くしてもいいよ」という姿勢でくるのだから、
これはもう、価格競争力の点で、太刀打ちできないのは当然である。
日本がTPPに参加し、農作物の関税撤廃を批准するなら、
日本はそのとき、アメリカや、
アメリカを越す自給率のオーストラリアやニュージーランドに伍せるくらいの、
食糧自給率を達成していることが求められる。
そうであれば、お互いさまで、
「おたくのも買うけど、ウチのも買ってね」で、商談成立だ。
だが現実的に、39%の自給率を100%超えにするのは容易ではない。
容易ではないが、減反政策を撤回し、農地利用を阻むルールを改正し、
潜在的な農業生産力を引き出す方向に政策を転換すれば、
100%超えとまではいかないにしても、
日本の自給率を飛躍的に上昇させることも不可能ではないだろう。
農作物をジャンジャンつくって、ガンガン輸出する。
そういう農業政策とセットであれば、
多少はTPP参加の意味も出てくるのかもしれない。
だが、そういう展開にはなっていない。
今のままで農産物の関税撤廃に応じれば、
価格をもう下げることのできない日本の農業が窮地に追い込まれ、
さらに、自給率を下げてしまうという悪循環を生み出すことになる。
もっともすでに過去の日記で書いているように、
TPPは、アメリカが日本の金融・保険・投資市場の開放を迫るものであり、
くわえて医療や公共工事(自治体単位のものも含めて)への参入も要求する、
「全面的攻勢」であり、
農作物の関税撤廃に関しては、
あくまで、その中のひとつにすぎないことを、あらためて確認しておきたい。
<一般社団法人起業支援ネットワークNICe 代表理事 増田紀彦>